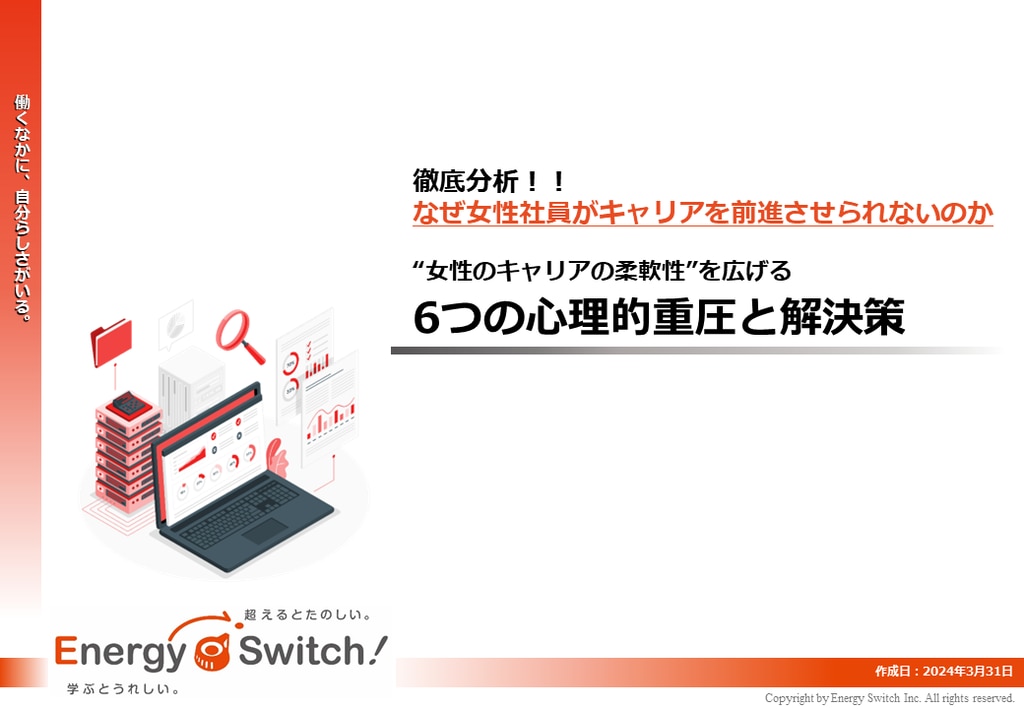【鍛え方がわかる】どんな仕事でも役に立つ!ロジカルシンキングの基本と実践、フレームワーク【研修事例あり】
この十数年で「ロジカルシンキング」はビジネスパーソンの必須スキルとして完全に
認知されるようになりました。しかし、その理解度や実際の仕事での活用度は、必ずしも
定着しているとはいえません。
改めて「あなたはロジカルシンキングが本当に出来ていますか?」と問われたら、
自信を持って出来ていると答えにくいのがロジカルシンキングの難しいところです。
なぜなら、日々の仕事で取り扱う情報は多岐にわたり、その整理や分析の難易度もさまざま。
わかりやすく説明するために必要といわれても、
わかりやすさの感じ方も人によってさまざまです。
ロジカルシンキングが必要とされるシチュエーションがあまりにも多いため、自分がどこまで
出来ているかもわからず、どうすればロジカルシンキングが向上するのかもよくわかりません。
今回のコラムでは、
ロジカルシンキングの基本、メリット、向上させるために必要な習慣などを紹介します。
目次[非表示]
ロジカルシンキングとは
ロジカルシンキングは日本語に訳すと「論理的思考力」というように、この言葉のとおり
「論理的に考える力」という意味です。
この論理的に考える力とは、何かについて考えるとき、道理や筋道に則ってより客観的な結論を
導く力であり、また、結論を導く際に必要な情報を細かく分析したり、ものごとの因果関係を
正しく整理する力も、この論理的思考力のなかに含まれます。
なぜロジカルシンキングが必要か
仕事では多くの人と関わりながら、さまざまな情報を扱います。
顧客の要望を汲み取り、それに応えるアイデアを出したり、問題が発生したときは、原因を分析し的確な対処も必要です。また資料作成や報告の場では、的確でわかりやすい説明が求められます。
このような日々の仕事の現場では、客観的に捉える視点、因果関係や情報を整理する力はなくてはならないものです。これがビジネスパーソンにロジカルシンキングが必要とされる理由です。
ロジカルシンキングのメリット
ロジカルシンキングが実践できるようになると、仕事において以下のようなメリットがあります。
・問題解決力の向上
仕事で問題が発生した際に求められるのは、正しい原因分析と適切な対策を考えることです。
ロジカルシンキングが実践できると、発生した問題について、事実と推測、経緯と現状、
対策案の費用対効果などをしっかり区別し、それらをつなぎ合わせながら最適な対策が
考えられるようになります。
・コミュニケーション能力が向上する
仕事では、その状況に応じた適切な説明が求められる場面がいくつもあります。たとえば、
専門的な内容から要点だけを抜き出して簡潔にまとめたり、その逆に作業手順の一つひとつを
丁寧に分解して説明するような状況です。
また相手に応じた説明が必要となるため、より客観的な内容にもしなければなりません。
ロジカルシンキングが実践できると、情報の要素分解やグルーピングでの整理、客観的な視点での考察をおこなうため、説明内容が的確になり相手に合わせた話し方ができるようになります。
・仕事の生産性が向上する
ロジカルシンキングが身につくと、情報の整理がうまくなるので、作業の段取りについて考える際なども効率の良いやり方が考えられるようになります。また誰かに説明したり、相手から説明を
受けるような場面でも、情報を整理しわかりやすくまとめられるようになるため、周りの人たちとのコミュニケーションも円滑となります。
総じて効率よく考えながら動けるようになり、他者と関わる仕事でも
認識の誤りが起きにくくなるため、日々の仕事全段の生産性が高まります。
ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、
ラテラルシンキング、それぞれの違い
◆ロジカルシンキングとクリティカルシンキングの違い 「論理的」と「批判的」
ロジカルシンキングは、事柄の因果関係や、2つ以上の情報をつなぎ合わせて結論を導く
思考法です。たとえば、なにか問題がありその対策を考えるとき、これまでの経緯、現状、
問題解決後の理想の状態などを検討の材料とし、それぞれの情報を要素分解したり、つなぎあわせながら最適な解決策を考えます。
一方、クリティカルシンキングは、批判的思考ともいわれ、思考する際の「前提」「論点」
「結論」に対して「これらは本当に正しいのか?」と自身で問いかけながら考える思考法です。
たとえば、同じように問題解決について考えるとき、「これまでの経緯や現状の認識は?」
「そもそも解決しなければいけないのか?」など、最初から思い込んでいるようなポイントに
対して、その認識が正しいのかを考えます。
仕事では、正確な情報であってもそれを断片的にしか捉えず、誤った結論を出してしまったり、
得た情報や前提が正しいと思い込んで、間違った方向で考えてしまうことがよくあります。
ここでロジカルシンキングとクリティカルシンキングの両方がうまく使えるようになると、
クリティカルシンキングで前提や論点を見直し、ロジカルシンキングで因果関係や各情報を
つなぎあわせ、結論が出た際もその結論が正しいのかを、クリティカルシンキングで再度見直してみることができるようになり、仕事における思考の精度全般が高まります。
◆ロジカルシンキングとラテラルシンキングの違い 「垂直思考」と「水平思考」
ロジカルシンキングは、物事を具体化しながらつきつめて考えたり、
原因について深堀して考えていく様子を指して「垂直思考」といわれることもあります。
その一方で、
「これ以外に考え方はないか?」
「前提条件をすべて無くしたら何が考えられるか?」
など、思考の制約をすべて取り除いて自由な発想で考えることを「水平思考」といい、
これはラテラルシンキングと呼ばれます。
ラテラルシンキングを練習するための有名な問題があります。
それは「10個のリンゴを3人で分けるとき、どうすれば公平に分配できるか?」
というものです。
多くの人は1人に3個ずつ分けて、残りの1個を3等分に切って分けると答えます。
しかし、正確に3等分することはなかなか難しいものです。
これをラテラルシンキングで考えると、10個のリンゴをすべてミキサーに掛けてリンゴジュースにして、それを3人で分けるという答えになります。
リンゴの形をリンゴジュースに変えてしまって良いのか?という疑問もありますが、確かに3等分にカットするよりも、ジュースを3つのコップに分けて注ぐほうが簡単に思えます。
このようにラテラルシンキングが身につくと、多くの人が常識的な思い込みのために、
最初から考慮する対象として除外してしまうものについても考えるようになり、
意外な解決策や誰も思いつかないアイデアが出てくることがあります。
ロジカルシンキングを鍛えるトレーニング方法
ロジカルシンキングを鍛えるには、日常のあらゆる場面で論理的に考える癖をつけることが
必要です。しかし、「これは論理的か?」という問いでは、どこからどう考えれば良いか
わかりにくく、答えにたどり着くまで時間もかかります。
ロジカルシンキングを向上させるためには、「論理的か?」と考える前に、以下の3つについて
考える癖をつけると、自然とロジカルシンキングの考え方が身につきます。
(1)「なぜ?」を考える
仕事で指示を受けたり、新しい作業に取り掛かるときなど、その仕事がなぜ必要なのか?
なぜこの作業が発生したのか?といった、仕事の目的や経緯について考えます。
たとえば、資料作成の仕事を始めるとき、
「なぜこの資料が必要なのか?」
「なぜこの様式になっているのか?」
「なぜこの日まで作らないといけないのか?」
を考えてみます。
そして、最初に出てきた結論が「〇〇の会議で必要だから」といったものであれば、今度は
「なぜ◯◯の会議では、その資料が必要なのか?」というように、なぜ?をどんどん掘り下げ
ながら考えていきます。
「それはなぜか?」を考えるくせが身につくと、物事の本質について考えるようになります。
また、考えても明確な答えが無いものは、仮説を立てながら、なぜ?を深掘りしていくので、
仮説検証をする力も鍛えられます。
(2)「客観的か?」を考える
なにかについて考え、結論を出したとき、それが「客観的な結論となっているか?」を考えます。
客観的か否かについて考える際は、一定の判断基準を決めておくと考えやすくなります。
たとえば、10人がその意見を聞いて8人以上が賛同できるか?納得できるか?といった
感じです。客観的か否か判断しようとすると、他の人の見方、一般常識とされている考え方など、
判断をするために様々な情報が必要なことに気づかされます。
このため、情報の集め方や分析のトレーニングにもなります。
客観的かどうかを考える習慣が除々についてきたら、対象を自身の考えだけでなく、職場での
他の人の意見、テレビ番組でのコメントなどについても考えてみると、客観的か否かを考える力がさらに向上します。
(3)「漏れやダブりがないか?」を考える
仕事で情報を整理するために一覧表を作ったり、問題解決策の選択肢などを挙げるとき、
そこに漏れやダブりがないかを考えます。
これは資料の記載ミスが無いように、何度も見直してチェックするという意味ではありません。
たとえば、仕事で問題が発生し、その原因について考えるとき、
「挙げた原因に漏れはないか?」
「言葉が違うだけで本質的には同じことを言っているダブりはないか?」
について考えてみるということです。
何かについて考える際、前提とするものに漏れがあれば、いくら考え方が正しくても、結論としては不十分なものになる可能性があります。また、整理した結果にダブりがあれば、結論に間違いがなくても、その内容を聞いた相手は混乱してしまいます。
日ごろから、漏れやダブりがない整理ができるようになると、考慮漏れを防いだり、説明が
わかりやすくなる効果があります。
ロジカルシンキング実践に役立つフレームワーク3選
ロジカルシンキングを実践する際に、役立つのがフレームワークです。フレームワークとは、
何かについて思考する際、その考える順番や、書き出して整理するための表や図の形式が、
あらかじめ定義されたものです。
フレームワークは、たくさんの人たちが長い年月を費やして考えてきたものであり、
効率よく確かな思考をするための先人の知恵といえます。
このフレームワークをうまく活用できると、考える順序や整理のかたちで悩むこともないため、
ただやみくもに思いつくものから考えたり、頭のなかだけで整理するよりも、何倍も効率よく
考えることができ、また思考の結果としても質の高いものになります。
ここでは、ロジカルシンキング実践に役立つ代表的なフレームワークを3つ紹介します。
「ロジックツリー」
考える対象について、その各要素をツリー上に書き出して整理するフレームワークです。
ツリー上に書き出すことで、要素分解やグルーピングを行う際、視覚的にわかりやすく
整理することができます。
また、ツリー上に書き出したものの上下の繋がりや、左右の並び方、記載の抽象度などに
違和感が無いかチェックすることで考えた結果の誤りや、漏れ、ダブりが見つけやすくなります。
さらに、書き出す際に、一定のルールを決めて各要素を書き出していく方法もあります。
たとえば、
・上段から下段へ「なぜか?」をひたすら書き出していくWHYツリー
・「どのようにおこなうか?」の選択肢を書き出していくHOWツリー
などがあり、これは原因分析や対策検討に役立ちます。
「重要度緊急度マトリックス」
仕事の優先度を考える際に役立つフレームワークです。
2本の線を縦と横で交わるように引き、縦の軸を重要度の高さ、横の軸を緊急度の高さとします。
こうすることで、
①重要度と緊急度の両方が高いもの
②重要度は高いが緊急度が低いもの
③重要度は低いが緊急度が高いもの
④重要度と緊急度が共に低いもの
の4つに分類する枠組みが出来上がります。
この4つの分類のあてはまるところに、自分がおこなっている日々の作業を、それぞれ書き出していくことで、作業の優先度がどうあるべきかを考えられるようになります。この2つの軸で4分割の枠を作り整理することを、4象限で整理するといいます。
このやり方を応用して2つの軸を、費用と効果、能力とやる気などにすることで、
対策の検討や、チーム体制を考えることにも役立ちます。
「3C分析」
Company(自社)、Customer(顧客)、Competitor (競合)の、3つのCを軸にして、それぞれの関係性を書き出して整理するフレームワークです。
営業や企画担当が、自社の方針や現状、顧客へ提供する価値について考えるときに、
このフレームワークが役立ちます。
たとえば、顧客から自社へは、長年受注している仕事がある、自社と競合は、同じ種類のサービスを提供しているライバル関係、競合から顧客へは競合のサービスに乗り換えるような猛烈な
アピールがされている。
このように3者の関係性を書き出してみることで、
自社が何らかの対策を考える必要性が浮かび上がってきます。
また、このフレームワークを応用し、3つのCを別のものに変えることで、
さまざまなものの関係性を整理することができます。
たとえば、中間管理職の人が自身の立ち位置を考えるときは、自分、チームメンバー、上司の
3者の立場の関係性で考えてみたり、新人社員が仕事の取り組み方を考えるために、
自分のスキル、仕事内容、協力者の3つの視点で考えてみるなどです。
何かについて考えるとき、とりあえず思いついたものから考えていくことも、
ひとつのやり方ですが、このやり方のみで結論を出そうとすると、考慮漏れや掘り下げが浅い
結論になりがちです。
ある程度思いつくものが出てきたら、
それらの共通点や情報の属性をまとめながら整理していくことが必要です。
また、この3C分析のように、考えるポイントやキーワードが最初から決まっていると、
そこから連想できる事柄が思いつきやすくなるので、効率よく考えることができます。
ロジカルシンキング(ベーシック)研修事例紹介
ここからは、弊社で実際に実施した、基礎編のロジカルシンキング研修の事例をご紹介します。
演習も含めた一日間の研修事例です。
【研修事例】
テーマ:
ロジカルシンキングベーシック
ねらい:
・ロジカルに考えることの要点を理解し、説明できるようになる
・相手を動かす伝え方を理解し、実践できるようになる
内容:
①オリエンテーション
トレーナーから、ロジカルシンキングを身につける必要性と本研修のねらいを説明し、
研修受講後も各自が成長のために何を取り組むべきかを意識してもらいます。
②ロジカルシンキングの概要
ロジカルシンキングの目的とメリットを説明し、
ロジカルシンキングの本質的な部分について解説します。
(1)ロジカルとはどういうことか
(2)ロジカルシンキングの3要点
③ロジカルシンキングトレーニング ~目的・整理・つながり~
演習に入る前にそれぞれの要点の重要性を解説し、実際に演習を繰り返すことで、
ロジカルシンキングスキルを鍛えます。
(1)「なんのために」を意識する(目的):目的の重要性と目的を考える力
(2)分けるとわかる(整理):わかるとわからないの違い、ものごとの整理分類方法
(3)つなげる(つながり):接続詞を使って結論と理由、主張と根拠を紐づける
④相手を動かす伝え方
わかりやすい伝え方の基本パターンを解説し、演習を通じて実践します。
⑤視野を広げる
相手の立場に立ってものごとを考えるために、視野を広げる練習をします。
⑥まとめ
研修全体を振り返りながら、ロジカルシンキングの必要性と具体的なアクションを再認識します。
(1)質疑応答
(2)振り返り
弊社では、個社ごとに完全オーダーメイドで研修をご提案しております。
パートナーとして協力いただいている外部トレーナーが450名以上おり、
個社ごとに合った研修をプロデュースしております。
ロジカルシンキングをテーマにした研修バリエーションも豊富です。
本記事を参考に、是非自社の目的や課題に合った研修を実施してみてはいかがでしょうか。